製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
ポンプなるほど
このコーナーでは、ポンプにまつわる様々な「専門用語」にスポットを当て、イワキ流のノウハウをたっぷり交えながら、楽しく軽やかに解説します。今まで「なんとなく」使っていた業界の方はもちろん、専門知識ゼロでもわかる楽しい用語解説を目指しています。文末の「今日の一句」にもご注目ください。クスッと笑えて記憶に刻まれるよう、毎回魂を注いで作っております。
「残留塩素」を見つめ続けて、早くも4回目のポンプなるほど。今回はちょっと目先を変えて、日頃使われている「塩素剤」にフォーカスしてみたいと思います。
そもそも塩素とは「原子番号17番」の元素ですが、私たちが一般的に「塩素」と呼ぶのは「塩素分子(Cl2)」であり、「塩素ガス」と呼ばれる気体です。
これらが「塩素」の特徴です。
さて、今回の主役「次亜塩素酸ナトリウム」は、その「塩素」と「水酸化ナトリウム水溶液」を化学反応させた物です。次亜塩素酸ナトリウム自体は固形ですが、化学的に不安定で分解しやすい性質があるため、水溶液として使うのが一般的です。
次亜塩素酸ナトリウム溶液はほんのり緑黄色の綺麗な液体です。どうすれば有効に使いこなすことができるのか? 危険はないのか? ポイントを軽くまとめてみました。
上水道、プール、循環型の温泉などの場所で使われている次亜塩素酸ナトリウム溶液は、濃度が12%です。これが一番使いやすい状態であると言われています。この12%濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液を、殺菌・消毒の様々な用途により、それぞれに適した濃度に希釈して使用します。用途によっては6%の溶液を使用する場合もあります。
次亜塩素酸ナトリウム自体が不安定な化合物ですので、常温でも徐々に自然分解していきます。日光、特に紫外線や温度の上昇とともに分解が促進されていき、殺菌・消毒する力が薄まってしまいます。
次亜塩素酸ナトリウムは、『毒物及び劇物取締法』や『消防法』が規定する危険物には指定されてはおりませんが、誤って酸と混合させると有毒な「塩素ガス」が発生し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
塩酸との反応で塩素ガスが発生
NaClO + 2HCl → NaCl + H2O + Cl2 (Cl2:塩素)
お酢やクエン酸でも混ぜると化学反応を起こし「塩素ガス」が発生します。刺激臭だけならまだしも、最悪死亡事故が起こる場合もありますので、取り扱いには十分な注意が必要です。
現在、殺菌・消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使うケースが増えていますが、ほかの塩素剤も健在です。塩素剤も適材適所。ほかの選択肢もあることを、この機会に覚えておいてください。
次亜塩素酸カルシウム(粉体・錠剤)
その昔、学校のプールに入れていたのは、こちらのタイプ。「さらし粉」や「カルキ」というネーミングの方が、馴染みがあると思います。固体ですので管理がしやすいのが最大のメリット。ただし、固まっているだけに湿気にはとっても弱いので、カラッとしたところで保管しておくことが鉄則です。
ちなみに、水道水を「カルキ臭い」とか、やかんで沸かして「カルキ抜き」するということがよく言われていますが、厳密に言うとそれは正しくはありません。なぜなら現在の浄水場は、次亜塩素酸ナトリウムの方を使っているから。でも、昔からの慣習で今でもそう言われているんですね。またまた豆知識でした。
電解次亜水
ヒーローの必殺技のような響きのある「電解次亜」は、塩水を電気分解して生成します。塩水があれば手軽に作ることができるので、自分のところに電解水生成装置を導入し、使っている工場などもあります。
他にも「有機系塩素剤(塩素化したイソシアヌル酸など 粉体錠剤)」や「液化塩素(高圧で液化したもの)」、機能水の類(次亜塩素ナトリウムや電解次亜を酸性溶液で中性〜酸性にして殺菌力を高めたもの)などがあります。余力があったら覚えておきましょう。
はい。ということで、今回は塩素について、まるで理科の授業のような内容になってしまいましたが、たまにはこういう回があってもよいのではないかと。
残留塩素の世界、まだまだ続きます。次回もお楽しみに。
今日の一句
ジァジァ〜っとほどよい効果でいろんな菌をやっつける
殺菌・消毒のスーパースター☆次亜塩素酸ナトリウム
次の記事へ
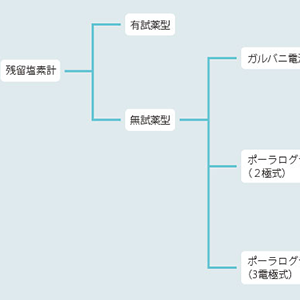
前の記事へ

製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ